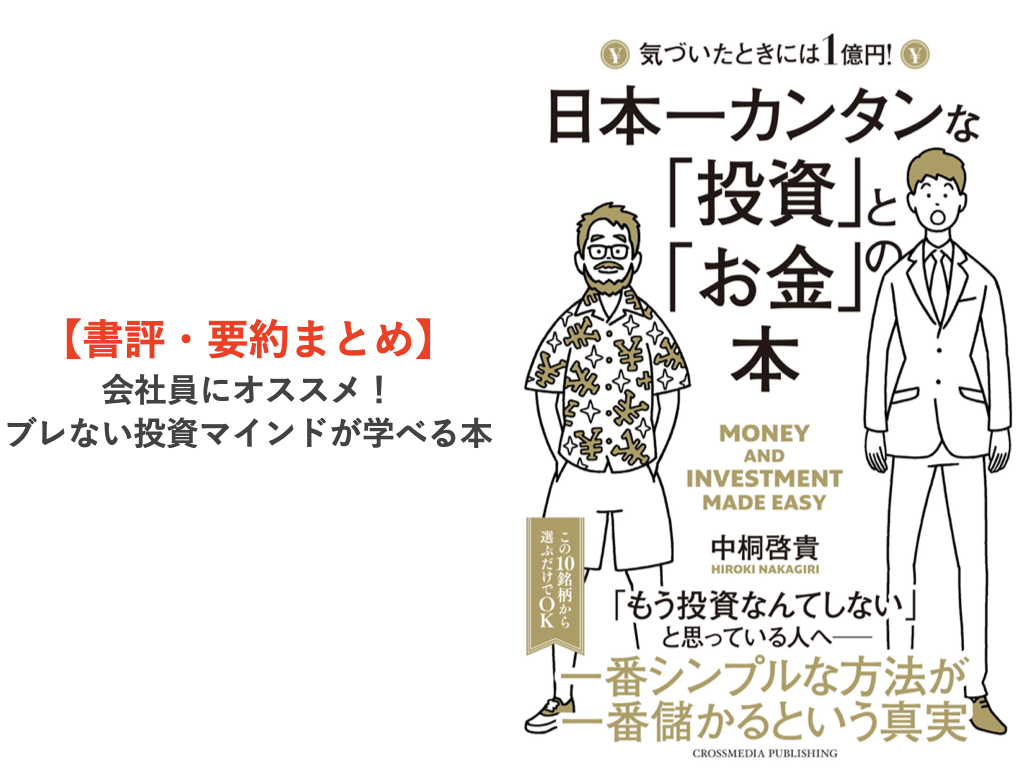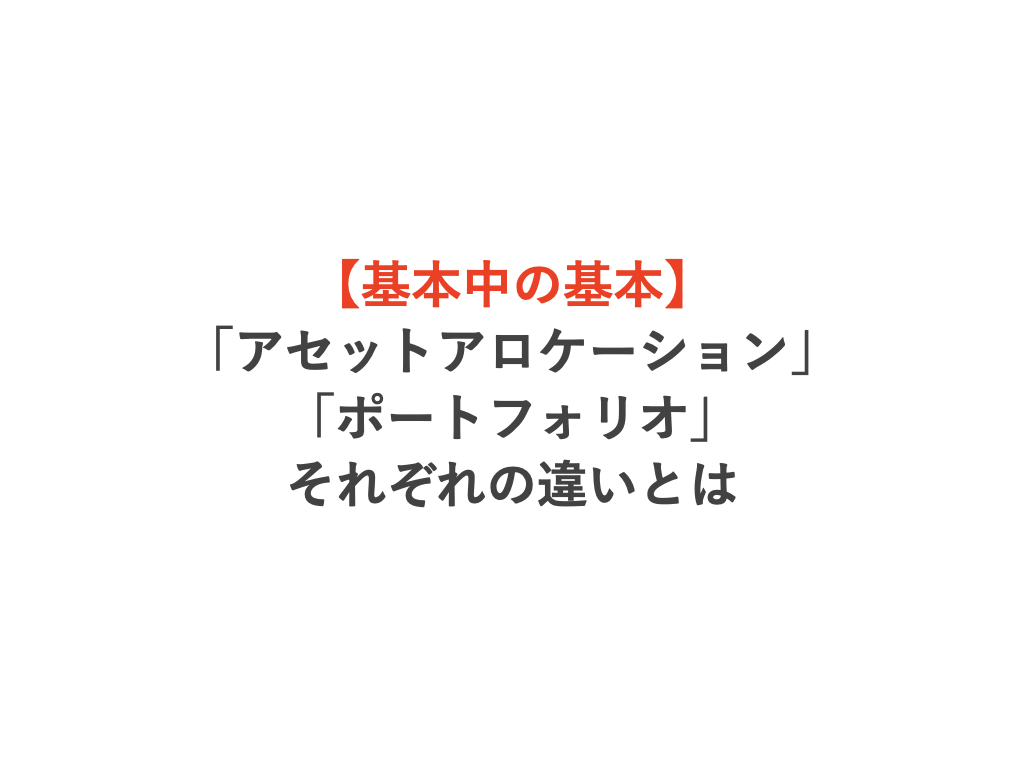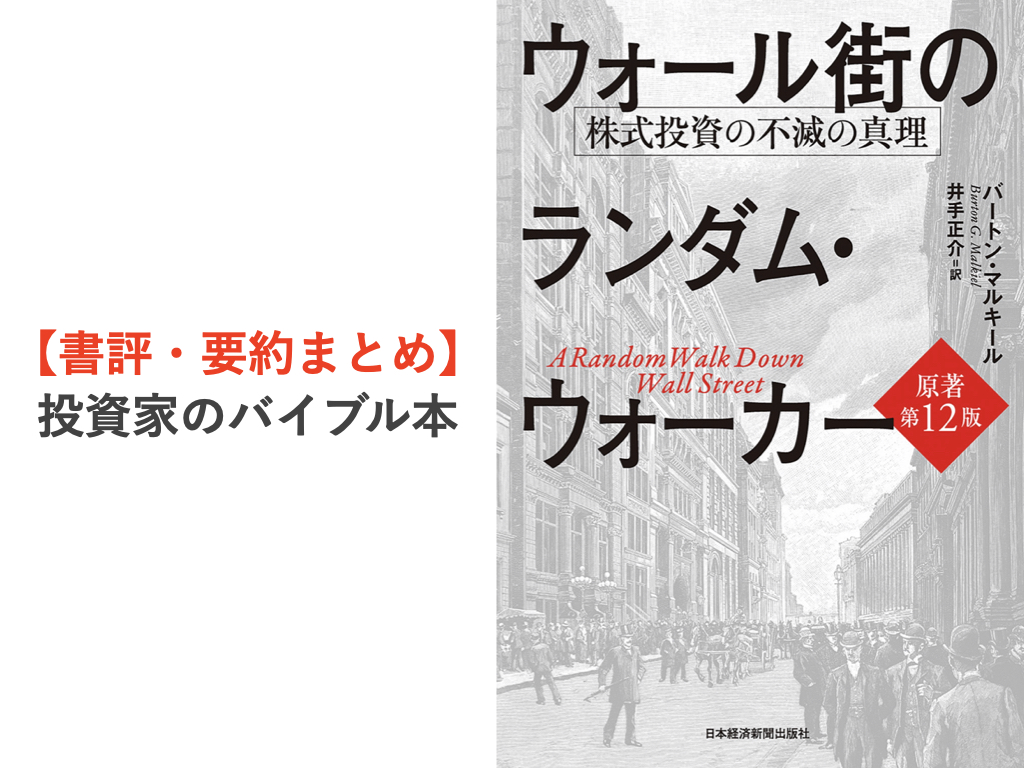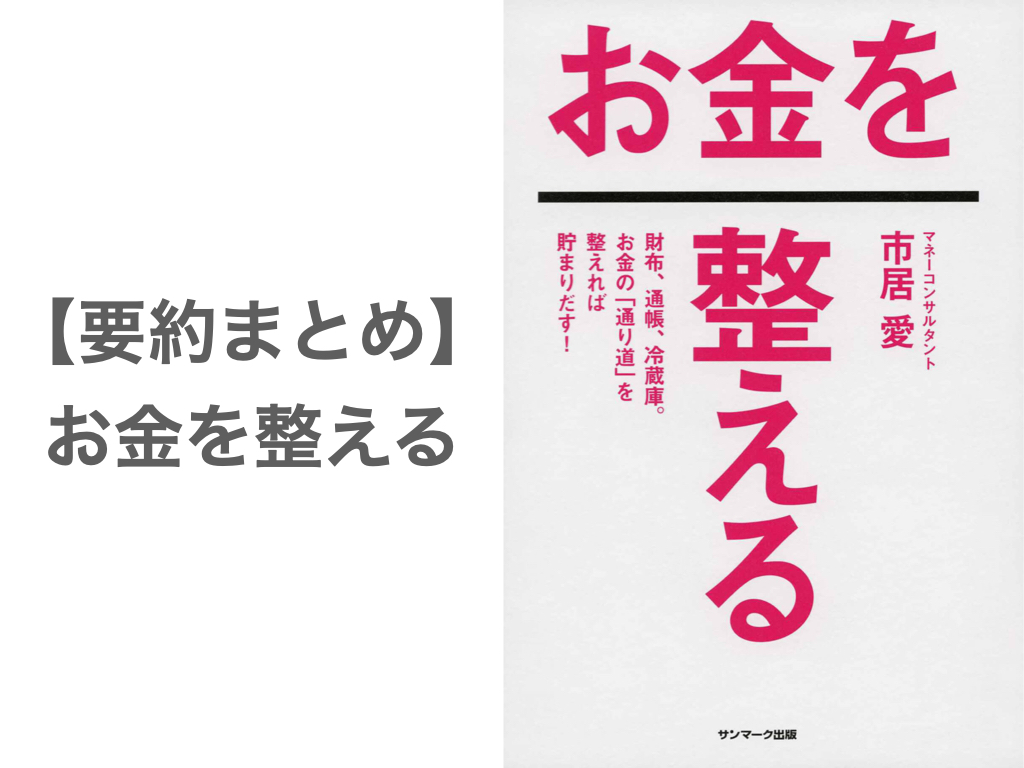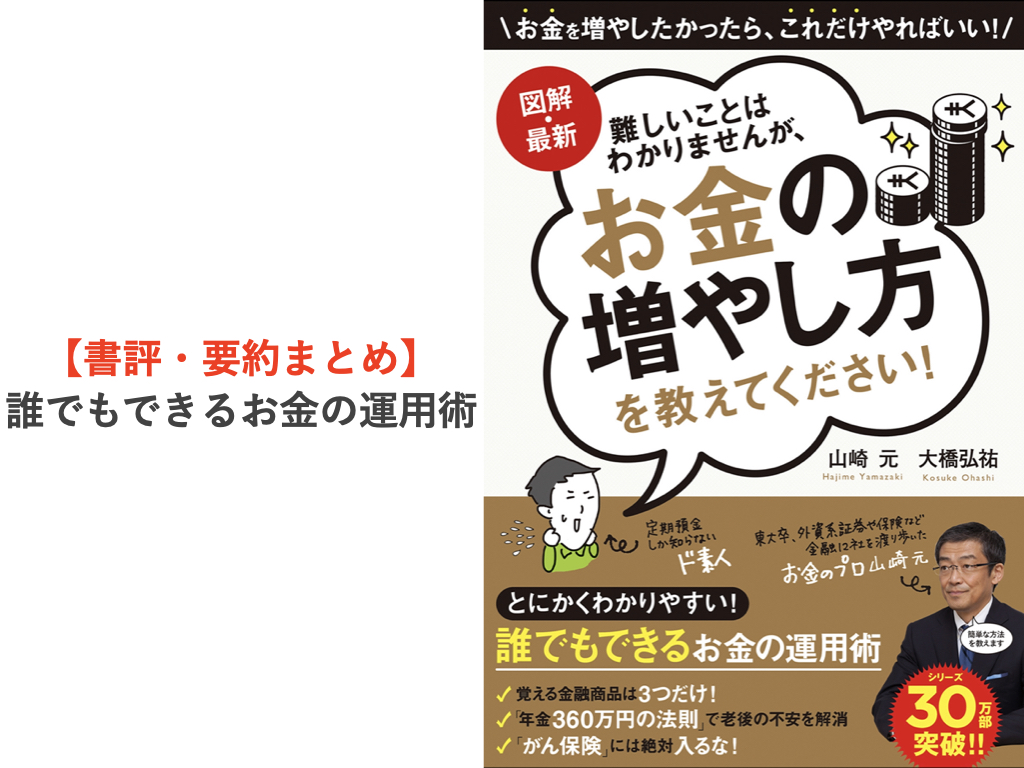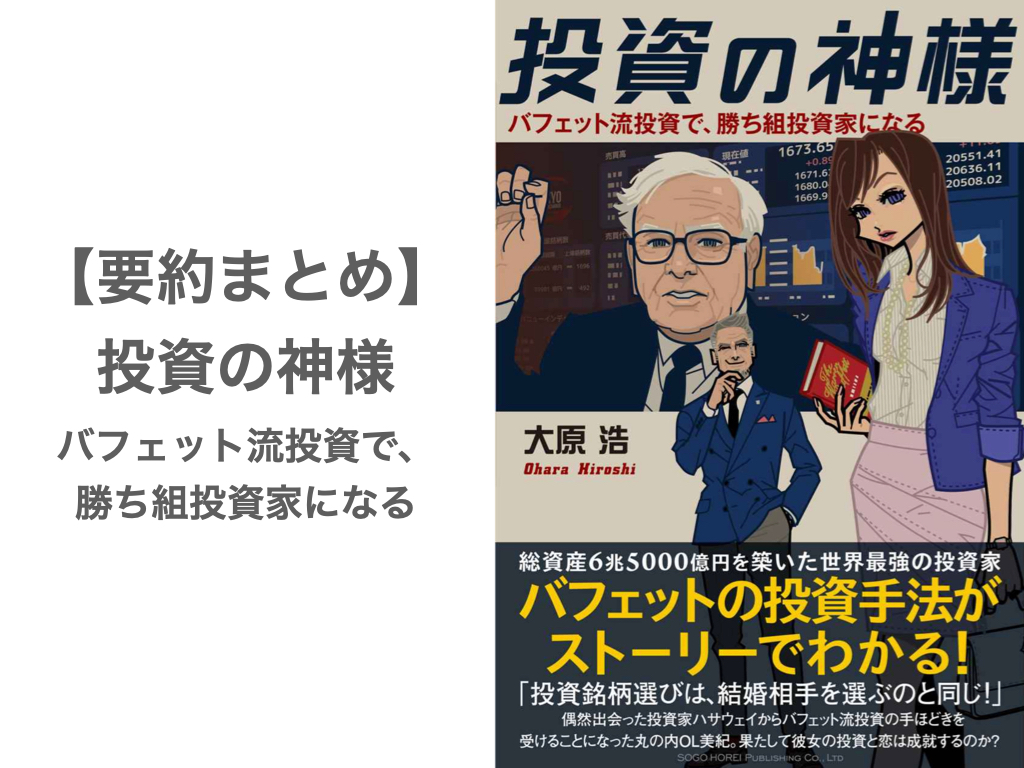【書評・要約まとめ】超簡単 お金の運用術(山崎 元さん著)〜99%の投資本が不要になる一冊〜
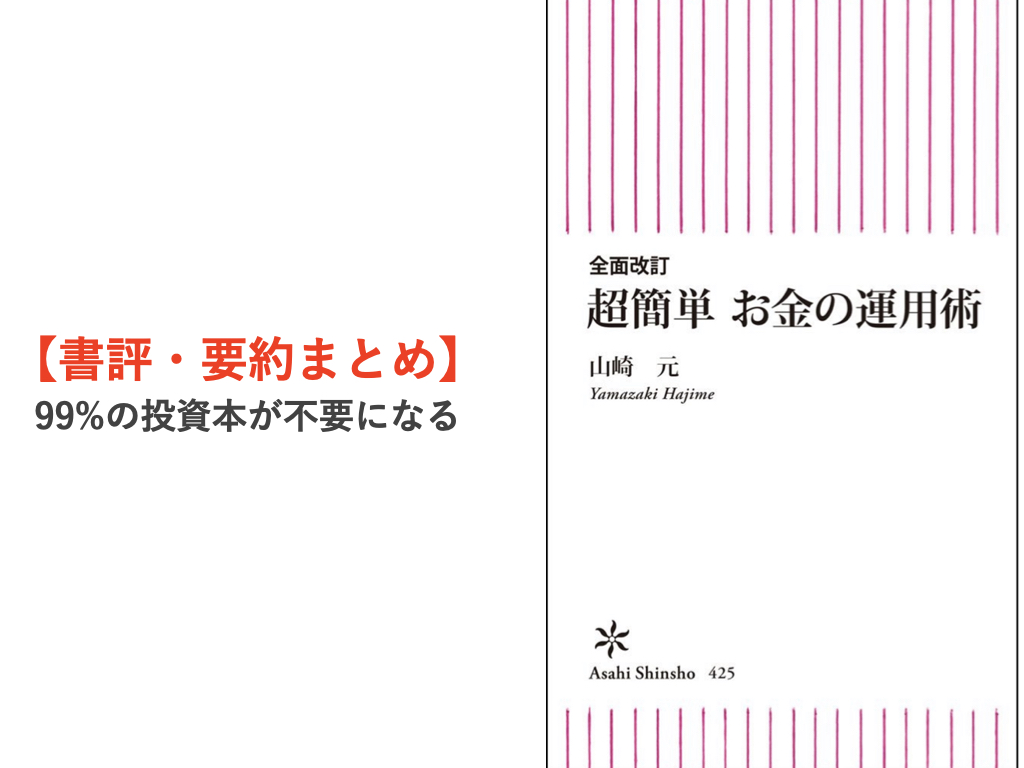
山崎 元さん著「超簡単 お金の運用術」を読めば、99%の投資本が不要になります。
2013年に全面改定版が出版された本なので、「古い」という理由で、読む対象から外してしまいがちかと思います。
しかし、書かれてある内容は、まったく色褪せることなく、今でも、これからも使える投資知識が詰まっています。
ベースとなるのは、インデックス投資ですが、非課税制度の活用や生命保険に関する考え方など、個人投資家にお役立ち情報がいっぱいです。
山崎 元さんは、楽天証券に勤めていることもあって、本書の内容にも、説得力があります。
「お金の取扱説明書」を意識して書かれたとあって、本当にわかりやすくてオススメの本です。
この記事では、山崎 元さん著「超簡単 お金の運用術」の書評・要約まとめをお伝えしていきます。
投資初心者の方は特に、よくチェックしてみてくださいね。
超簡単なお金の運用方法
本書では、冒頭から、いきなり具体的なお金の運用方法が書かれています。
よくある投資本のように、著者の投資遍歴などが紹介されておらず、必要な情報をスッと読むことができるのがいいです。
というのも、本書を書いた目的について、このように言われているからです。
本書は、現役世代のビジネスパーソンや主婦に広く役立つように書いたつもりだが、同時に、個人的には、遠くに住んでいる老親に一冊渡しておくと安心な「お金の取扱説明書」であることを意識して書いた。
両親のために書いたのなら、余計な内容が省かれていることも納得です。
このうえで、著者は、このようにも言っています。
本書の目的は、
(1)極めて簡単だけれども、
(2)現実的にほぼベストに近くて、
(3)無難なお金の運用方法を、
読者にお伝えすることにある。
僕、個人の感想としては、まさにこの通りの内容だと感じています。
著者も言うとおり、本書の内容を実践することがベストな運用方法だなと納得しています。
では具体的に、どんな運用方法なのかをご紹介していきますね。
生活防衛費を確保する
本書では、まず最初に、3ヶ月分程度の生活費を、銀行の普通預金に置いておくことが必要と言われています。
名著「ウォール街のランダム・ウォーカー」「敗者のゲーム」でも言われているくらいなので、どこまでいっても大切なことです。
投資をしているけど、生活防衛費を用意していない人は、少しずつでも蓄えておくのがよいでしょう。
残りを「リスク運用マネー」「無リスク運用マネー」に分割する
リスク運用マネーとは、利回りが高いけど、最悪、1年で3分の1が失われる可能性があるお金。
無リスク運用マネーは、ほぼ元本割れの心配をせずに済むお金。
この2種類に分けて、投資をすることがオススメされています。
リスク運用マネーを「国内外インデックスファンド」に投資する
リスク運用マネーは、国内インデックスと先進国インデックスに、半分ずつに分けて投資するのがベターとのこと。
ちなみに,国内インデックスは「TOPIX連動型上場投資信託」、先進国インデックスは「SMTグローバル株式インデックス・オープン」の名前が上がっています。
どちらのファンドも、本書が出版された2013年から購入していれば、かなり上昇していることがわかります。
現時点で、必ずしもこの2つを選ぶ必要はないと思いますが、「インデックス最高!」ということに変わりはないでしょう。
手数料の安いファンドがたくさんあるので、ご自身で探してみてくださいね。
我が家では、「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」に、積立投資中です。
無リスク運用マネーを「個人向け国債」「MRF」で持つ
無リスク運用マネーの投資対象は、2つあります。
あまりリスクを大きく取りたいない投資家さんは、これらの投資対象をポートフォリオに組み込むことで、資産全体のリスクを軽減することができます。
自分の投資スタイルにあった、投資を心がけましょう。
大きな支出が生じたら、躊躇なく解約して充てる
投資している目的は、将来のためというのがメインの理由かと思います。
しかし、大きな支出が生じたら、躊躇なく解約して充てることも必要になってきます。
もし、解約せずに借金をした場合には、投資益よりも高い金利を支払うことになってしまいます。
僕自身も、自動車の購入や結婚など、大きな支出のときに、積立投資を解約した経験があります。
「あのお金を、今でも運用していたら」と思うことはありますが、割り切って解約したことで、いまの幸せがあるのだと思っています。
解約するときのルールは、ご自身の投資方針書などに記載しておくのが良いでしょう。
NISA、確定拠出年金を最大限利用する
NISAや確定拠出年金といった税制優遇制度は、最大限利用することがオススメです。
活用する場合は、リスク運用マネーを選びましょう。
もちろん、運用コストは、なるべく安いものを探してくださいね。
お金のあれこれレクチャー
ここまで資産運用についてご紹介してきましたが、本書のいいところは、これだけではありません。
運用以外の、僕たちが気になるお金のあれこれについても解説してくれているのです。
具体的には、こちらの内容について、特に詳しく書かれています。
【レッスン1】経済循環と資産運用
【レッスン2】インフレ・デフレでとるべき資産運用は異なるか?
【レッスン3】個人が陥りがちな運用の「罠」は?
【レッスン4】外国為替は投資に向くのか?
【レッスン5】資産運用の中で住宅の位置付けは?
【レッスン6】生命保険の正しい選び方は?
【レッスン7】退職金の運用で気を付けることは?
【レッスン8】アドバイザーの選び方
【レッスン9】「投資力」を鍛えるには?
【レッスン10】ギャンブルとの付き合い方は?
どれに気になる内容ですが、人に相談しにくいことばかりですよね。
そんな事柄について、著者がわかりやすく解説してくれているので、僕も、大変参考にさせてもらいました。
まとめ
本書は、2013年に出版された本ですが、今でも現役で活用することができる内容ばかりです。
投資もですが、お金の基本ルールは、時が経ったからといって、簡単に変わるものではないですからね。
働き世代である僕たちをメインターゲットとしつつ、老若男女に役立つ内容がしっかりと盛り込まれています。
大切なお金をどのように扱っていいか迷いのある人は、ぜひ読んでみてください。